施工管理の離職率が高い原因とは?防止する方法も紹介
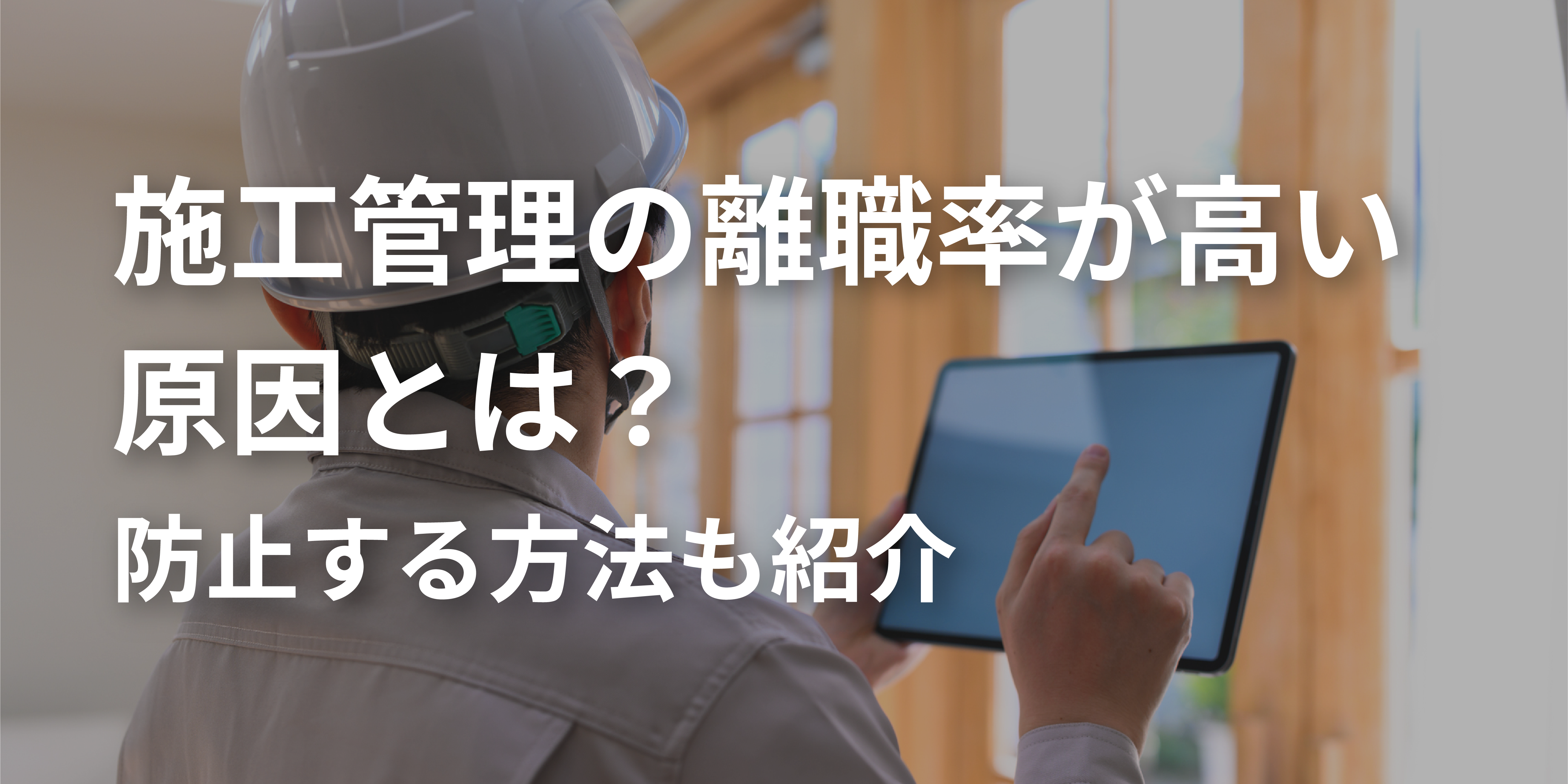
施工管理職の離職率が高いなどと悩んでいませんか。人材の育成に悩んでいる方も多いでしょう。施工管理職の離職は、建設業界全体が直面している課題です。主な離職の原因として、労働環境や待遇の厳しさが挙げられます。ここでは、建設業界の離職率を紹介するとともに、施工管理職が離職する理由、施工管理職の離職を防ぐ方法などを解説しています。現状を正しく理解して、具体的な対策を講じたい方は、ぜひ参考にしてください。
建設業界の離職率はどれくらい?
一般的に、施工管理職が属する建設業界は、離職率が高いといわれています。国土交通省が発表している資料によると、建設業における新卒入職者の3年目までの離職率は大卒者が30%程度、高卒者が40~50%程度です。これらの値は、同じ条件の製造業を上回っています。具体的な離職率は以下のとおりです。
| 卒業年度 | 建設業(大卒) | 製造業(大卒) | 建設業(高卒) | 製造業(高卒) |
|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 30.1% | 18.6% | 50.0% | 27.6% |
| 2013年 | 30.4% | 18.7% | 48.3% | 28.7% |
| 2014年 | 30.5% | 20.0% | 47.7% | 28.9% |
| 2015年 | 28.9% | 19.5% | 46.7% | 28.0% |
| 2016年 | 27.8% | 19.6% | 45.3% | 28.8% |
| 2017年 | 29.5% | 20.4% | 45.8% | 29.2% |
| 2018年 | 28.0% | 19.0% | 42.7% | 27.2% |
| 2019年 | 28.6% | 18.5% | 40.7% | 26.3% |
| 2020年 | 30.1% | 19.0% | 42.5% | 27.6% |
若年労働者の確保が困難になっていることが読み取れます。就業者数が減少している点にも注意しなければなりません。建設業就業者数の推移は以下のとおりです。
| 年度 | 建設業就業者数(万人) |
|---|---|
| 2012年 | 503 |
| 2013年 | 499 |
| 2014年 | 505 |
| 2015年 | 500 |
| 2016年 | 492 |
| 2017年 | 498 |
| 2018年 | 503 |
| 2019年 | 499 |
| 2020年 | 492 |
| 2021年 | 485 |
| 2022年 | 479 |
2002年(618万人)との比較で約22%減少しています。人材面では厳しい状況が続いているといえるでしょう。
出典:(pdf)国土交通省「建設業(技術者制度)をとりまく現状」 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001715124.pdf
出典:(pdf)厚生労働省「-令和4年雇用動向調査結果の概況」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/23-2/dl/gaikyou.pdf
施工管理の離職率が高い原因
続いて、施工管理職の離職率が高い理由を解説します。
長時間労働・休日出勤の常態化
離職率が高い理由として、長時間労働・休日出勤の常態化が挙げられます。施工管理職に限ったデータではありませんが、2022年度における産業別年間実労働時間は調査産業計より68時間長い、産業別年間出勤数は調査産業計より12日多いことが示されています。施工管理職は仕事量の兼ね合いから、労働時間、出勤数とも多くなりやすい傾向があります。たとえば、納期に間に合わせるため、残業せざるを得ないこともあるでしょう。ワークライフバランスをとりにくいため離職率が高いのです。ただし、建設業にも時間外労働の上限規制が適用された(2024年4月から)ことで状況は変わる可能性があります。
出典:(pdf)国土交通省「建設業(技術者制度)をとりまく現状」 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001715124.pdf
出典:(pdf)厚生労働省「建設業の事業主の皆さまへ 建設業『時間外労働の上限規制』のポイント」 https://www.mhlw.go.jp/content/001232856.pdf
過酷な労働環境
厳しい労働環境も、離職率を高めている原因といえるでしょう。施工管理職は、現場に出かけて常駐しなければなりません。炎天下の中、あるいは寒空の中、業務を行うこともあります。騒音が発生する環境、事故と隣り合わせの環境で、業務を続けなければならない点もポイントです。肉体的なストレスだけでなく、精神的なストレスもかかります。負担の大きさに耐えられず、離職を選択する方もいます。
人間関係のストレスや職責の負担
人間関係の悩みも、離職の原因になりえます。施工管理職は、クライアント、現場の職人、会社の上司などと連絡調整を行いながら業務を進めなければなりません。それぞれの利害が対立すると、板挟みになって強いストレスがかかります。たとえば、経験不足を理由に、現場の職人がクライアントと調整した指示を守ってくれないなどが考えられるでしょう。ここに、職責の重さが加わる点もポイントです。安全管理を第一に据えつつ、工程管理、原価管理、品質管理も行わなければなりません。さまざまなストレスがかかるため離職率が高くなるのです。
業務量に見合わない給与水準
ここまでの説明でわかるとおり施工管理職の業務はハードです。この点に配慮して、給与水準はやや高めに設定されています。厚生労働省が運営している職業情報提供サイト「job tag」によると、建築施工管理技術者の年収は641.6万円(全国平均)、土木施工管理技術者の年収は596.5万円(全国平均)です。ただし、これらの給与水準でも業務量に見合わないと感じる方が少なくありません。また、企業規模や勤務地によっては、全国平均より給与が低いこともあります。待遇に関する不満で離職する方もいます。
出典:職業情報提供サイトjob tag「建築施工管理技術者」 https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/21
出典:職業情報提供サイトjob tag「土木施工管理技術者」 https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/23
プロジェクトに合わせた転勤の多さ
プロジェクトにより勤務地が変わる点も、離職率が高い原因のひとつといえるでしょう。ケースによっては、単身赴任などの形で一定期間にわたり遠方で勤務しなければならないことがあります。結婚や出産などをきっかけに、働きにくさを感じる方もいます。
若手・女性育成体制の不備
若手や女性の教育体制が整っていない点も、離職率を高めている原因と考えられます。効率よく学べない、自信をもって業務を進められないなどの不満が溜まるためです。具体的な教育環境は事業者で異なりますが、徒弟制度のような教育しか行っていないところもあります。一昔前の若手、女性と現在の若手、女性の考え方は大きく異なります。時代にあわせたアップデートを行えていないと、採用した人材が早期に離職することもあるでしょう。
施工管理の離職を防止する方法
続いて、施工管理職の離職を防ぐ方法を紹介します。
適切な労務管理
施工管理職の労働時間、年間休日、給与、福利厚生などを適切に管理すると、離職率は低くなる傾向があります。これらに関する不満を抱きにくくなるためです。ただし、具体的な見直しのポイントは事業者で異なります。自社の改善点がわからない場合は、実際に働いている施工管理職を対象にヒアリングやアンケート調査を実施するとよいかもしれません。
DXの推進(施工管理システムなど)
DX化を推進することでも、離職率を引き下げられる可能性があります。業務を効率化して、施工管理職の負担を軽減できるためです。経済産業省は、DXを以下のように定義しています。
デジタル技術やツールを導入すること自体ではなく、データやデジタル技術を使って、顧客目線で新たな価値を創出していくこと。 引用:(pdf)経済産業省「デジタルガバナンス・コード実践の手引き(要約版)」 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-chushoguidebook/tebiki-yoyaku.pdf
具体的な取り組みの例として、施工管理アプリの導入が挙げられます。工程表を簡単に作成できる、進捗状況をチーム全体で共有できるなどのメリットを期待できます。業務の効率化に効果的です。
ハラスメント対策や定期面談
それぞれの従業員が働きやすい環境をつくることも大切です。良し悪しは別にして、昔ながらの風習、文化が残っている建設現場が少なくありません。たとえば、上司が部下に強い口調で指示をだすなどが考えられます。行き過ぎた言動は、パワーハラスメントと捉えられる可能性もあります。トラブルが発生する前に、研修を実施するなど、ハラスメント対策を講じておくことが重要です。従業員が抱えている悩みを把握したい場合は、定期面談を実施するとよいでしょう。
適切な人事評価に基づく昇給・賞与
適切な人事評価制度の導入も、離職率を引き下げるポイントです。施工管理職のモチベーション向上にもつながります。重視したいポイントは次のとおりです。
| 重視したいポイント | 概要 |
|---|---|
| 公平性 | 好き嫌いではなくルールに基づき評価する |
| 客観性 | 誰が見ても納得できる具体的な評価基準を設ける |
| 透明性 | 評価のプロセスを明確にして開示する |
以上を意識すると、納得感を得やすい人事評価制度をつくれます。離職率の引き下げだけでなく、生産性の向上も期待できるでしょう。
柔軟な働き方の導入(フレックスタイムや在宅勤務など)
仕事と家事、出産、育児、介護、治療などの両立で悩む方は少なくありません。仕事を続けたくても、辞めざるを得ない方もいるでしょう。フレックスタイム制度や在宅勤務制度など、柔軟な働き方を導入すると環境を問わず働きやすい職場になります。競合他社がよく似た制度を導入していなければ、自社で働き続ける大きな理由になるはずです。
教育制度の整備(資格取得支援やメンターなど)
キャリアアップにつながる教育制度を導入すると、若手社員のモチベーションを維持しやすくなります。具体的な取り組みとして、資格取得支援制度の導入などが挙げられます。人事評価制度と連動させると高い効果を期待できるでしょう。若手社員が孤立しやすい場合は、上司とは別の先輩社員がサポートするメンター制度を導入するとよいかもしれません。相談役を設けることで、定着率を高められる可能性があります。
まとめ
建設業における新卒者の離職率は30~50%程度です。就業者数の減少を踏まえると、何かしらの対策が必要といえるでしょう。具体的な取り組みとして、労務管理や人事評価制度の見直しが挙げられます。あるいは、DX化の推進も効果的です。住宅会社・工務店向けの施工管理アプリに興味がある方は、現場Plusの導入を検討してみてはいかがでしょうか。期間を入力するだけで工程表を作成できる、ワンタッチで進捗報告できるなど、現場に必要な機能を標準搭載しています。月額1万円~利用できる点や導入前後に手厚いサポートを受けられる点も魅力です。詳しい製品情報は、以下のページでご確認ください。
現場Plus公式サイトはこちら






