建設・建築業界にテレワークが広がらない理由とは?実施率や導入のポイント
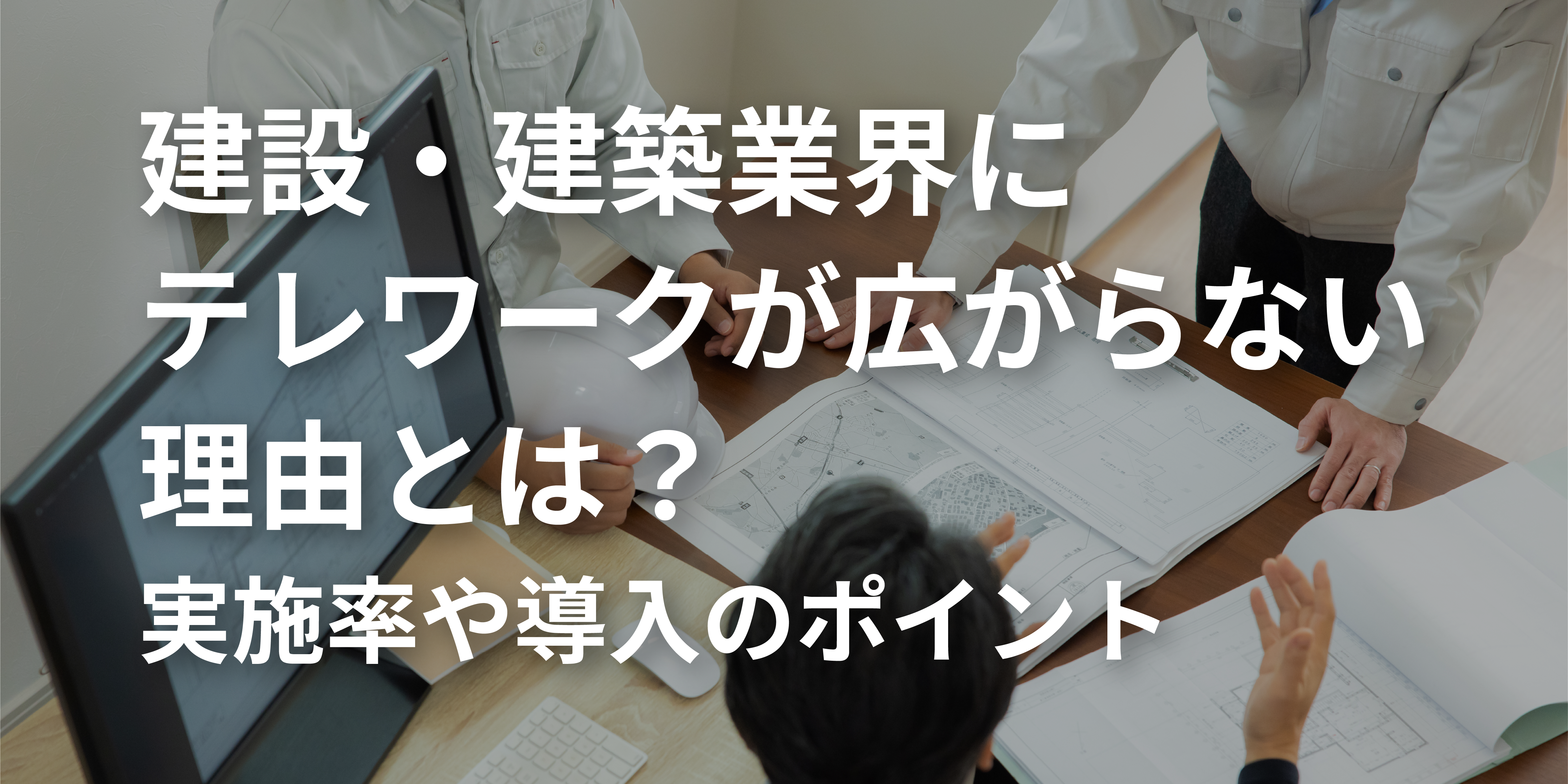
他業界に比べて、建設・建築業界はテレワークが浸透していません。現在でも、昔ながらのやり方が残っているケースが多いといえるでしょう。見方を変えると、テレワークの導入により競合他社と差をつけられるチャンスです。市場で優位なポジションを築ける可能性があります。ここでは、建設・建築業界におけるテレワークの実施率を紹介するとともに、同業界でテレワークが普及しない理由、テレワークを導入する際に意識したいポイントを解説しています。業務効率や生産性を高めたい方は参考にしてください。
建設・建築業のテレワーク実施率はどれくらい?
国土交通省が発表している資料によると、建設・建築業でテレワークをしたことがあると回答した方の割合は以下のとおりです。
| 分類 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|
| 雇用型テレワーカー | 28.4% | 26.4% |
| 自営型テレワーカー | 15.1% | 16.7% |
産業計の値は示されていないものの、他業界に比べるとテレワークをしたことがある方の割合は低いといえるでしょう。 参考までに、情報通信産業の割合は72.8%、不動産業の割合は34.4%、製造業の割合は32.6%です(いずれも、2023年雇用型テレワーカーの値)。
中小企業に限定すると、値はどのように変化するのでしょうか。中小企業における業種別テレワーク実施率は以下のとおりです(東京23区の中小企業が対象。2022年5月16日~26日に調査を実施)。
| 業種 | テレワーク実施率 |
|---|---|
| 建設業 | 23.6% |
| 全体 | 29.7% |
| 製造業 | 31.6% |
| 卸売業 | 38.2% |
| 小売業 | 7.1% |
| サービス業 | 31.3% |
2022年2月時点に比べ、建設業の実施割合は13.1ポイント減少しています。減少幅は、全業種の中で最大です。
出典:(pdf)国土交通省「令和5年度テレワーク人口実態調査-調査結果(概要)」
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001733057.pdf
出典:(pdf)東京商工会議所「中小企業のテレワーク実施状況に関する調査」
https://www.tokyo-cci.or.jp/file.jsp?id=1029704
建設・建築業界にテレワークが広がらない理由
以上のデータが示すとおり、建設・建築業界にテレワークはあまり浸透していません。主な理由として以下の点が挙げられます。
工事現場で主な作業が行われる
建設・建築業界の仕事は、現場で行う業務とオフィスで行う業務にわかれます。現場で行う業務の中には、テレワークが適していないものもあります。代表例としてあげられるのが、足場の組立・解体・撤去、電気工事、内装工事などです。このような業務の割合が高いため、他の業種に比べてテレワークが浸透していないといえるでしょう。ただし、現場で行う業務の中にも、テレワークを活用できるものはあります。具体例として、事務作業や打ち合わせなどが挙げられます。現場における業務がすべてテレワークに適していないと決めつけず、改善の余地を探る姿勢が求められます。
アナログ作業が多い
アナログ作業を行っている事業者が多い点も、テレワークの浸透を妨げる要因の一つです。たとえば、以下のような業務が挙げられます。
【アナログ業務の例】
- 作業日報の作成
- 勤怠管理
- 施工管理
- 在庫管理
- 安全管理
たとえば、現場で紙の作業日報に記入する、紙の出勤簿で始業時刻や終業時刻を管理するなどが考えられます。従業員がアナログ業務に慣れていると、テレワークの導入に拒否感を抱くこともあります。
業務が属人化している
アナログ作業の弊害として、業務が属人化しやすいことが挙げられます。ここでいう属人化とは、特定の従業員だけが業務内容を把握している状態を指します。簡単に説明すると、担当者不在では業務を進められない状況といえるでしょう。業務の属人化は、テレワークの導入を妨げる要因になりえます。ルールや手順を統一しないと、テレワーク下では業務の品質を維持しにくいためです。
労働者のITスキルが不足している
労働者が習得しているITスキルにばらつきがあることも、テレワークの浸透を妨げている要因と考えられます。全体のITスキルが一定レベルに達していないと、テレワークを導入しても効率よく活用できないためです。ITツールを使いこなせない労働者がいたり、ITツールが業務の妨げになったりする恐れがあります。これらのリスクが想定されるため、テレワークの導入が進んでいないといえるでしょう。
建設・建築業界にテレワークを導入する際のポイント
ここからは、テレワークの導入にあたり意識したいポイントを解説します。
工事現場とテレワークの業務を整理する
前述のとおり、建設・建築業界の業務は以下の2つにわかれます。
【業務の種類】
- 工事現場で行う業務
- オフィスで行う業務
オフィスで行う業務は、テレワークと相性が良いといえるでしょう。工事現場で行う業務は、テレワークと相性が良い業務と悪い業務にわかれます。前者の代表例として事務作業、後者の代表例として足場の組立が挙げられます。テレワークを導入する前に、対象になる業務、ならない業務を整理することが大切です。近年になって、工事現場で活用できるITツールの開発が進んでいます。さまざまな業務に対応できるようになっているため、自社だけで判断できない場合は開発会社へ相談してみるとよいかもしれません。
デジタル化・ペーパーレス化を推進する(クラウドシステム・通信設備・セキュリティシステムなど)
デジタル化・ペーパーレス化を推進すると、テレワークを導入しやすくなります。テレワークに対応できる環境が整うためです。たとえば、作業日報をデジタル化しておくと、混乱することなくテレワークに移行できる可能性が高くなります。具体的な取り組みとして、通信環境を整える、ITツールを導入するなどが挙げられます。遠隔地から操作できるクラウドシステムは、テレワークと相性が良いといえるでしょう。テレワークを導入する際は、セキュリティにも十分な注意が必要です。原則として、情報漏洩のリスクは高まります。必要に応じて、セキュリティ対策を講じることが重要です。
業務を標準化する
テレワークにもさまざまな課題が存在します。一例としてあげられるのが、従業員間でコミュニケーションをとりにくいことです。それぞれの従業員が自己流で業務を進めると、効率が悪くなったり、生産性が低下したりする恐れがあります。これらのリスクを回避するために取り組みたいのが業務の標準化です。業務の標準化は、ルールやプロセスを統一して担当者による品質のばらつきをなくすことといえるでしょう。業務を標準化する基本的な流れは以下のとおりです。
【標準化の流れ】
- 標準化の対象になる業務を洗い出す
- 1で洗い出した業務に優先順位をつける
- 作業プロセスをマニュアルとして明文化する
- 実際に業務を行って課題を見つける
- 課題に対応できるようにマニュアルを修正する
共通のルール、プロセスができると、テレワークで作業効率を高めやすくなります。
ITリテラシー教育を推進する
ITリテラシーにばらつきがあると、テレワークを導入しにくくなります。従業員により、できること、できないことが異なるためです。ITツールの選定にも大きな影響を与えます。したがって、テレワークを導入する前に、能力の底上げを目指して、ITリテラシー教育を行っておくことが大切です。具体的な取り組みとして、研修の実施、資格取得の支援、ICT環境の整備などが挙げられます。能力の底上げには一定の時間がかかるため、長期的な視点で取り組みを進めていくことが大切です。
まとめ
建設・建築業界におけるテレワークの実施率は20~30%程度です。浸透していない理由として、テレワークに向かない業務がある、属人化している業務が多いことなどが挙げられます。対処法のひとつとして、業務の標準化が挙げられます。業務の標準化には、ITツールの活用が有効です。導入しやすい製品をお探しの方は、DX化を後押しする注文分譲クラウドDXや現場Plusを候補に加えてみてはいかがでしょうか。営業・用地・工事・経理・経営まで、関連する情報をクラウド上で一元管理できます。詳しい機能などは、以下のページでご確認ください。
注文分譲クラウドDX公式サイトはこちら
現場Plus公式サイトはこちら






