エクセル(Excel)で受発注管理を行う方法とは?作り方とメリット・デメリット・注意点を解説
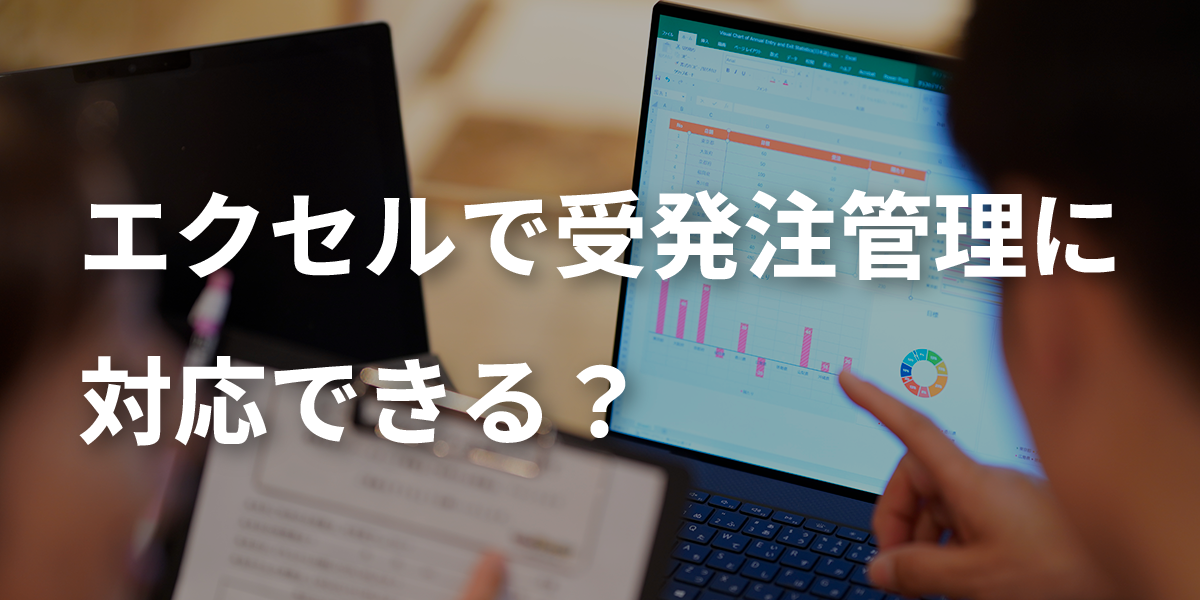
受発注管理をエクセルでできないかと検討している担当者は多いのではないでしょうか。
エクセルでの受発注管理はコストを抑えつつ、手軽に始められるため、小規模事業者やスタートアップではまず候補にあがります。
しかし、汎用性が高く簡単に利用できる反面、複数部署での共有が難しく属人化しやすいというデメリットもあります。
本記事では、エクセルで受発注管理を検討している方に向けて、メリット・デメリット、手順、システム導入の考え方までを解説します。
エクセルで受発注管理に対応できる?
エクセルを活用した受発注管理は多くの企業で行われており、充分に対応可能です。
ただし、業務が複雑になってくるにつれてエクセルでの受発注管理が非効率に感じることも少なくありません。
ここではエクセルでの受発注管理のメリット・デメリットや活用の際のポイントについて詳しく解説します。
メリット
エクセルでの受発注管理の最大のメリットはコストがあまりかからない点です。
エクセルは普段の業務ですでに利用している企業が多く、新たにシステムやソフトを購入する必要がありません。
また業務で利用しているので、操作方法などもわかっているため、利用がスムーズに進む点もメリットでしょう。
またエクセルは汎用性が高く、カスタマイズが柔軟に行えるため、関数やマクロの知識がある社員がいれば、自社の運用に適した受発注管理表を作成することも可能です。
関数やフィルター、条件付き書式などを活用することで、集計や色分け、進捗状況の見える化なども実現可能です。
また、オフラインでの利用も可能なため、インターネット環境がなくても利用できる点も特長です。
デメリット
一方でエクセルのデメリットは属人化しやすい点にあります。
シート構成や関数・マクロの組み込みなど、担当者に依存する面が多いことから、引継ぎや共有がうまく行われず、業務が属人化しやすい傾向にあります。
また、複数人での同時作業には向いておらず、共有中のファイルが上書きされたり、変更履歴が追えなくなったりする恐れがあります。
さらに、データの破損や消失などのリスクも高くなっており、運用が煩雑になるケースも多くなっています。
ポイント
上記の通り、エクセルには自社仕様の柔軟な受発注管理表を作成できるという利点はありますが、多人数での管理には不向きです。
つまり少人数でシンプルな受発注管理を行う場合には、エクセルでの運用が有効といえます。
ただし、関係部門が複数にわたる大規模工事が多くなってきたり、発注件数が増加してきたりした場合はエクセルでの対応は難しく、専用の受発注管理システムの導入も検討した方が良いでしょう。
エクセルで受発注管理に対応する手順
次にエクセルで受発注管理に対応するための手順について解説します。
必要な項目を洗い出す
まずは受発注管理に必要な項目を洗い出します。受発注管理に必要な項目には以下のようなものがあります。
- 発注日
- 会社名
- 連絡先(所在地・電話番号・メールアドレスなど)
- 担当者名
- 商品の分類・種別
- 商品名
- 商品のサイズ・色
- 発注数
- 商品単価
- 商品の型番・商品コード
- 商品のJANコード
- 受注日
- 使用する配送会社・配送日
- 納期
- 進捗状況
項目の洗い出しでは、必要な項目を初めから網羅しておくことが重要です。漏れがあると後からの追加や修正に手間がかかるため、事前に丁寧な確認を行いましょう。
表のレイアウトを設計する(またはテンプレートを活用する)
項目が確定したら、各種データを入力する表のレイアウトを作成します。一般的には列に項目名、行に案件ごとのデータを入力する形式が一般的です。
入力のしやすさや視認性を意識して、レイアウトを工夫しましょう。
入力規則やセルのサイズ調整をしておくことで、視認性を高め、入力ミスを防ぐ工夫をしておくことも大切です。
また受発注管理表は、インターネット上で提供されているテンプレートを活用することで、レイアウト作成を効率化できます。
その場合は、自社の業務フローや必要項目に微調整するようにしましょう。
関数やフィルターなどの機能を活用する
受発注管理表を作成する際には、関数やフィルターなどの機能を活用し、入力や管理の効率化を図りましょう。
エクセルには関数やフィルター機能などが豊富に用意されています。エクセルには、関数やフィルター機能などが豊富に用意されています。たとえば、SUM関数を使用して自動集計を行ったり、条件付き書式を使って納期遅延の案件を目立たせたりするとよいでしょう。
また業務が複雑化してきた場合は、VLOOKUPを活用して、マスターデータから情報を自動取得する仕組みを構築するのも有効です。
ただし、関数を過剰に設定すると属人化が進んだり、メンテナンスが複雑化したりする可能性があるため注意が必要です。
またピボットテーブルやグラフ機能の活用もおすすめです。
ピボットテーブルは、エクセルに入力されたデータの合計や平均などを自動で算出・集計できる機能です。
発注データを取引先別にまとめたり、月別に推移を確認したりすることで発注傾向を把握することができます。
グラフ機能はデータの集計結果を視覚的にわかりやすく表示することが可能です。
視覚的に表示することで、データの傾向や変化が把握しやすくなるため、積極的に活用しましょう。
運用ルールを設定する
エクセルの管理を安定して続けるためには、運用ルールの策定が不可欠です。
入力者・確認者・更新者などの役割を明確にし、ファイルの命名ルールや保存場所、更新頻度なども社内で統一しましょう。
特にバックアップの取得は重要で、定期的に別ファイルとして保存する仕組みを設けておくことで、万が一のトラブルに備えられます。
また、共有ファイルを使う場合は、誤操作防止のためにシート保護を設定したり、Googleスプレッドシートなどで変更履歴を確認できる環境を整えたりすることもおすすめです。
受発注管理システムがおすすめ
ここまでご説明した通り、受発注管理システムをエクセルで作成・運用することは可能です。
しかし、発注量が増え、業務が複雑化するにしたがって、エクセルでの管理には限界が出てきます。
とくにエクセルのデメリットである属人化、共有の難しさなどは受発注管理システムのほうが秀でています。
受発注管理システムは発注や受注管理はもちろんのこと、協力会社とのやり取りや納品・請求・支払管理もシステム上でスムーズに連携が可能です。
またクラウド上で情報が共有されるため、現場や協力会社との連携も場所を選ばず可能なため、労働環境の改善やテレワークなどの働き方改革にもつながるでしょう。
株式会社ダイテックでは建設業向けに特化した受発注システムクラウドサービス 受発注Plus を提供しています。
ご興味のある方はぜひ一度ご確認ください。
受発注Plus公式サイトはこちら
まとめ
本記事ではエクセルでの受発注管理について、メリットやデメリット、作成の手順などについて詳しく解説しました。
エクセルでの受発注管理は初期コストもあまりかからず、汎用性も高いため、小規模な企業などでは有効な選択肢です。
しかし、発注量が増えたり複数人で管理したりするようになれば、限界も見えてきます。
ある程度の規模になった段階で、より安定した業務フローのためにも早めに受発注管理システムへの意向を検討しましょう。
株式会社ダイテックでは建設業向けに特化した受発注システムクラウドサービス 受発注Plus を提供しています。
受発注管理や納品/査定・請求・支払管理など建設業で必要な機能に絞っており、操作もシンプルになっているので、導入後すぐに使用することが可能です。
受発注管理システムの導入を検討している担当者の方はぜひご検討ください。
受発注Plus公式サイトはこちら






