受発注業務とは?基本的な流れ・課題・解決策を解説
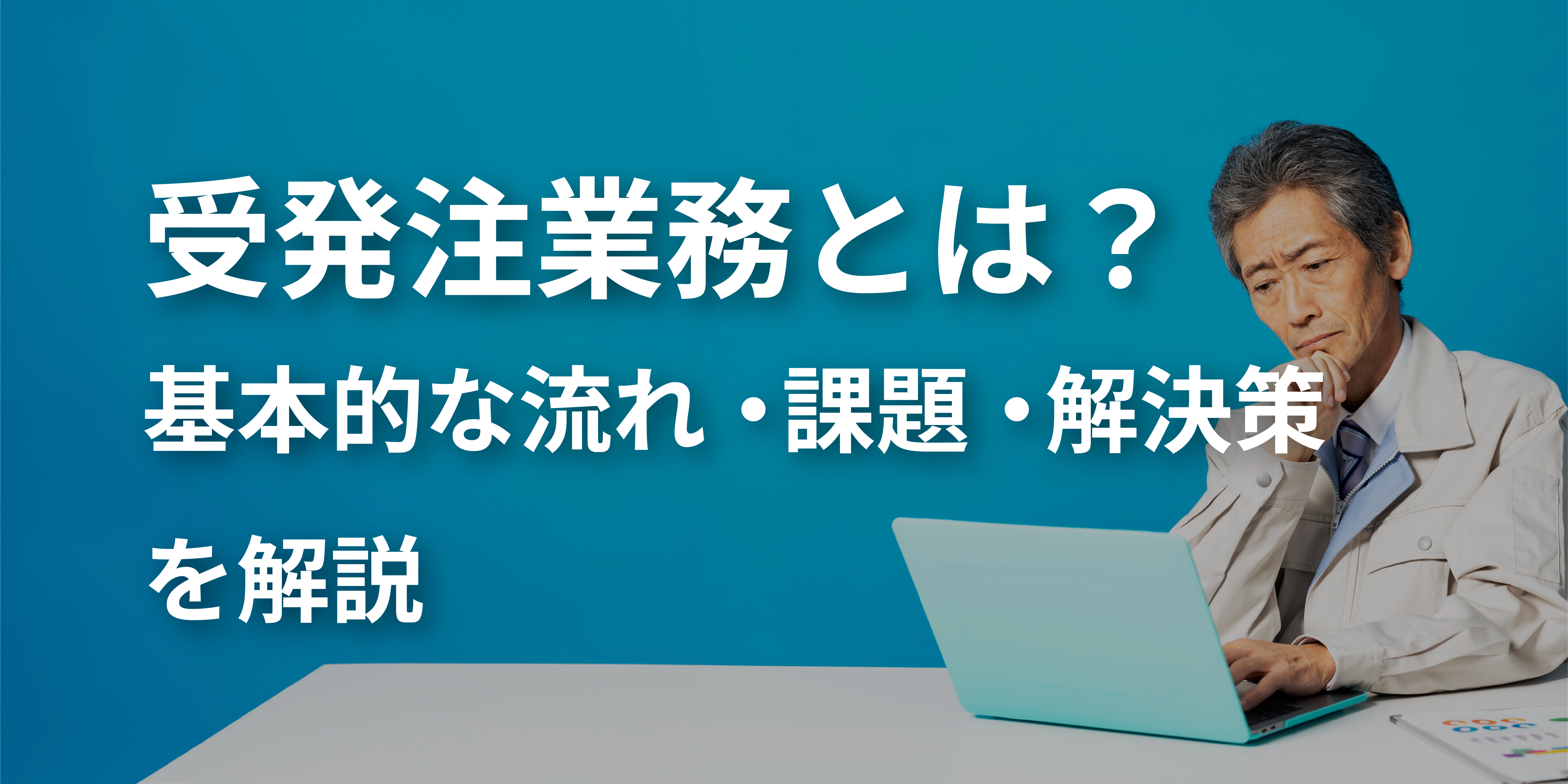
受発注業務は、企業経営を支える重要な業務です。複数のステップで構成されるため、さまざまな課題が発生することが少なくありません。主な課題として、業務の煩雑さ、属人化などがあげられます。これらの課題に対処することで、業務効率や生産性の向上が期待できます。ここでは、受発注業務の概要を解説するとともに、受発注業務で遭遇しやすい課題と各課題の解決策を紹介しています。業務の効率化などに取り組んでいる方は参考にしてください。
受発注業務とは?基本的な流れを紹介
受発注業務は、取引先へ注文を出す業務、取引先が注文を受ける業務の総称です。具体的に、どのような流れで進められるのでしょうか。受発注業務の基本的な流れを解説します。
見積り
最初のステップは見積もりです。基本的には、以下の流れで進みます。
【見積もりの流れ】
- 発注側の事業者が見積もりを依頼
- 受注側の事業者が製品、数量、納期などの要件を確認
- 受注側の事業者が見積書を作成して提出
発注側の事業者が、複数の事業者へ見積もりを依頼することもあります。
契約の締結
見積書の内容に問題がなければ、発注側の事業者が受注側の事業者へ発注書を送付します。これを受けて、受注側の事業者が折り返しの連絡、あるいは注文請書を送付し、発注側の事業者がいずれかを受けた時点で契約は成立します。
商品の発送・受領
受注側の事業者が、準備した商品の検品と梱包を行います。これらに問題がなければ、納品書を添付して商品を発送します。ただし、すべてのケースでこれらの作業を行うわけではありません。事業内容によっては、これら以外の方法で商品やサービスを提供することもあります。発注側の事業者は、注文通りの商品が届いていることを検品で確かめます。
支払い・請求
受注側の事業者が請求書を送付します。発注側の事業者は、請求書の内容に従い、期日までに代金を支払います。入金を確認した受注側の事業者が、領収書を送付して受発注業務は完了です。
受発注業務の課題
受発注業務には、さまざまな課題があります。主な課題は以下のとおりです。
業務の煩雑さや属人化
一般的に、受発注は煩雑な業務といわれています。取引先により契約条件などが異なるためです。基本的には、一定の経験を要する業務といえるでしょう。手作業で行っている場合は、業務が属人化してしまうケースが少なくありません。業務の属人化は、特定の従業員しか業務の進め方などを理解していない状況です。たとえば、取引先から「いつもと同じで」といわれて受注している場合は、属人化している可能性が高いといえます。一見すると問題ないように思えますが、担当者が何かしらの理由で不在になると受発注業務を行えなくなります。業務の停滞を招くため、十分な注意が必要です。
業務負担の大きさ
受発注業務の負担が大きくなることもあります。主な理由として以下の点があげられます。
【業務負担が大きくなる理由】
- 少人数で対応している
- 入力作業に時間がかかる
- 取扱商品や取引先の数が多い
受発注業務が複雑化していると、周囲の人員がサポートできないため、担当者にかかる負担は大きくなる傾向があります。特定の日に受発注が集中する場合も注意が必要です。担当者に大きな負担がかかると、モチベーションの低下を招いたり、受発注に関わる業務が滞ったりする恐れがあります。
アナログ作業によるミス
アナログ作業によるミスも、受発注業務で遭遇しやすい課題です。ここでいうアナログ作業は、電話やFAXを使った受発注業務といえるでしょう。具体的には、次のミスなどが起こりやすくなります。
【起こりやすいミス】
- 電話で注文内容を聞き間違える
- FAXの内容を読み間違える
- 注文内容を転記、入力するときに間違える
これらのミスが、大きなトラブルにつながることも考えられます。たとえば、注文とは別の商品を送ってしまうこともあります。リスクを理解して、対策を講じることが重要です。
連携不足によるコスト増加
部門間の連係不足で、無駄なコストがかかることもあります。たとえば、在庫管理を行う物流部門と連携が取れずに過剰な在庫を抱えてしまう、逆に在庫切れで販売機会を失ってしまうなどが考えられるでしょう。あるいは、情報共有に手間がかかり、受発注業務の効率が悪くなることや納品リードタイムが長くなることも考えられます。ケースによっては、取引先にも悪影響を与えるため注意が必要です。
受発注業務の課題解決策
続いて、受発注業務の課題を解決する方法を紹介します。
情報の一元管理と共有(受発注管理システムの導入)
業務の煩雑さは、業務プロセスを明らかにすると解消できる可能性があります。何をどの順番で行えばよいかが明らかになるためです。手順を整理する過程で、無駄な作業も発見できます。同様に、受発注管理システムの導入も効果的です。同システムは、受発注業務の各プロセスをデジタル化して一元管理するシステムといえるでしょう。具体的には、以下の機能などを備えます。
【基本的な機能】
- 受注管理
- 出荷管理
- 請求管理
- 他システムとの連携
受発注管理システムを導入すれば、アナログ作業に起因するミスも起こりにくくなります。
業務マニュアルの整備
業務マニュアルの整備も取り組みたい対策です。取り組みを怠ると、業務の属人化が起こりやすくなります。担当者の裁量の余地が大きくなるためです。たとえば、効率の悪い手順やミスが起こりやすい手順で、受発注業務を行うようになることも考えられます。
業務マニュアルを作成すると、このようなトラブルを防げるうえ、担当者が不在のときに他の従業員が受発注業務に対応できます。加えて、受発注管理システムを導入すれば、情報を共有できるため、特定の従業員に依存しない体制を構築しやすくなるでしょう。業務の効率化、生産性のアップを期待できます。
業務の可視化
業務の可視化にも取り組む必要があります。受発注業務の無理や無駄をなくすためです。ここでいう可視化は、受発注業務に関する5W1H(誰が・いつ・どこで・なにを・どのように)を明らかにすることといえるでしょう。可視化の基本的な流れは以下のとおりです。
【可視化の流れ】
- 現在の業務を明らかにする
- 課題を抽出して改善策を検討する
- 業務プロセスに改善策を導入する
- 3.をフローチャートで表す
- 4.に従い受発注業務を行う
改善策として、無駄な業務をなくす、よく似た業務をまとめる、システムを導入するなどがあげられます。以上の取り組みにより、ミスを減らすとともに受発注業務の負担を軽くできます。
業務委託・BPOの活用
受発注業務の委託、あるいはBPOの活用によっても、課題の解決を目指せます。業務委託は業務プロセスの一部を委託すること、BPOは業務プロセスの全体を委託することといえるでしょう。いずれにせよ、一定のスキルと経験を有する外部の人材に受発注業務を委託できるため、さまざまな課題の解決につながります。たとえば、担当者の負担を軽減して、コア業務に集中しやすくするといったことも可能です。ただし、依存度が高くなると、社内にノウハウを蓄積しにくくなります。メリット・デメリットを踏まえたうえで、利用することが重要です。
まとめ
受発注業務は、発注と受注に関連する業務の総称です。見積もり、契約締結、商品の発送・受領、請求・支払いの順で進みます。主な課題として、業務が煩雑になりやすいことや業務の負担が大きくなりやすいことがあげられます。解決策として検討したいのが、受発注管理システムの導入です。受発注管理システムには、幅広い業種に対応する汎用型と、特定業界向けに設計された特化型があります。株式会社ダイテックが提供する 受発注Plusは、住宅建設業に特化したサービスです。発注管理、納品査定、支払管理、受注管理、請求管理、支払通知確認など、電子受発注に必要な機能を網羅しており、元請と協力会社の間でのやり取りをスムーズに進められます。詳しい製品情報は、以下のページでご確認ください。
受発注Plus公式サイトはこちら






