施工管理の働き方改革が難しい理由とは?実現のポイントも解説
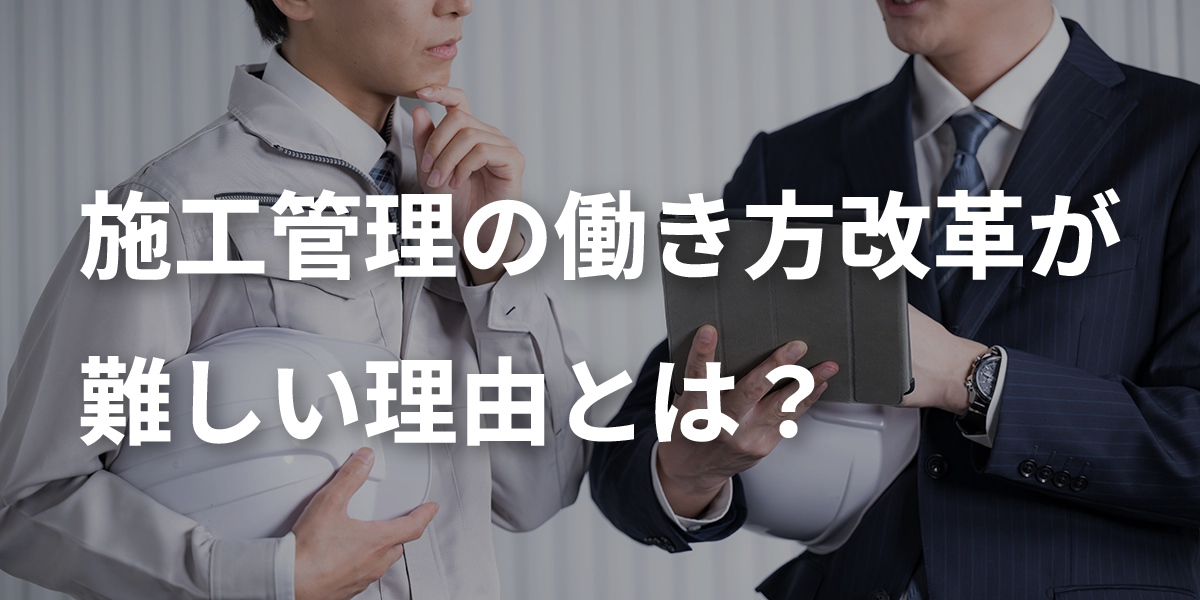
各業界で働き方改革が進んでいる中、施工管理の現場では、長時間労働や人手不足の影響で、働き方改革が進みにくいのが現状です。
本記事では、施工管理の働き方改革が進んでいない理由を6つの視点から詳しく解説します。
また、働き方改革を実現するためのポイントについてもご紹介します。
施工管理の働き方改革が難しい理由
施工管理の働き方改革はなぜ進まないのでしょうか。
ここでは施工管理の働き方改革が難しい理由を6つの視点から詳しく解説します。
慢性的に人手が不足している
1つ目の理由は、慢性的に人手が不足していることです。
施工管理だけに限らず、建設業界全体で人手不足は深刻な課題となっています。人口減少に伴い、今後は人材不足の深刻化が予測されています。
施工管理は建設業界の中でも専門性が高く、業務の幅が広いため、即戦力となる人材が限られていることも、人手不足に拍車をかけています。
1人あたりの業務負担が増加してしまい、長時間労働の温床となるなど、労働力不足は働き方改革を阻害する大きな要因となっているといえます。
長時間労働が常態化している
2つ目の理由は、長時間労働が常態化していることです。
施工管理の業務は、工程管理・安全管理・品質管理・原価管理など多岐にわたります。契約締結や書類の作成、トラブル対応なども業務範囲です。
加えて、現場での突発的なトラブルが発生することも多く、時間外での対応が必要になるケースも珍しくありません。
このように業務量の多さや時間的拘束が、長時間労働の常態化を招いています。
現場ごとにスケジュールが異なる
3つ目の理由は現場ごとにスケジュールが異なっていることです。
建設現場ごとに異なるスケジュールで進行することが多く、加えて天候や資材の納入、協力業者の状況によって日々スケジュールが変更になることも少なくありません。
施工管理者はこれらの状況に対して臨機応変な対応力が求められるため、ルーティン化が困難です。
複数現場を同時に担当している施工管理者も多く、スケジュール調整の負担が精神的なストレスや残業の増加につながることもあります。
アナログな方法を採用している
4つ目の理由はアナログな方法を採用しているからです。
建設業界では、いまだに紙の図面や手書きの日報など、アナログな業務が多く残っており、デジタル化が進んでいません。
アナログな業務が残っていることにより、現場に出ていた施工管理の担当者は書類作業のために事務所へ戻ったり、上司の承認を待ったりと、業務外の時間が発生しています。
作成業務の負荷に加えて、移動や承認待ちなどの時間のロスが多く発生していることも、施工管理の働き方改革が進まない理由といえるでしょう。
発注者や協力業者との関係性に左右されやすい
5つ目の理由は、発注者や協力業者との関係性に左右されやすいことです。
施工管理の業務は自社だけで完結することが少ない業務です。
発注者からの急な仕様変更や協力会社の作業遅延など、外部要因によって業務やスケジュールが大きく左右されます。
これらの影響を受け、無理のあるスケジュールを進めざるを得ず、負担が増すこともあります。
経営者の意識の問題
6つ目の理由は、経営者の意識の問題です。
企業によっては、現場の大きな負担や残業の多い労働環境などにあまり関心がなく、働き方改革の必要性を感じていないケースもあります。
働き方改革は有給休暇の取得や残業時間の抑制、業務負担の分散など、制度整備やIT投資といった経営判断が不可欠です。
経営者の意識が低く、現状の課題を解消する必要性を感じていなければ、これらの変化が起こらず、働き方改革は進まないでしょう。
施工管理の働き方改革を実現させるためのポイント
次に具体的に施工管理の働き方改革を実現させるためのポイントを6つの要素から詳しく解説します。
ICT活用による業務の効率化・自動化
1つ目のポイントは、ICT活用による業務の効率化・自動化です。
工程管理や日報作成などをクラウドベースに置き換え一元化できる施工管理アプリを使えば、業務の見える化と自動化ができ、現場作業や移動にかかる時間の大幅な削減に期待できます。
株式会社ダイテックが提供する施工現場管理アプリ現場Plusは、施工管理に特化し現場作業を効率化するために設計されたアプリです。
月額1万円から利用でき、工程表や図面、写真などのクラウド化による情報共有の迅速化・円滑化を図れる他、入退場管理や協力業者への多段承認など、施工現場に必要とされる機能を幅広く備えています。
詳しくはこちらにてご紹介していますので、施工管理の効率化をご検討の方は、ぜひ参考にしてみてください。
マニュアル整備による業務標準化
2つ目のポイントはマニュアル整備による業務標準化です。
施工管理で働き方改革が進みにくい背景の一つに、業務の属人化が挙げられます。
特定の人にしかわからない業務があると、その人に負担がかかり残業時間を短縮することができません。
こういった属人化しがちな業務を標準化するためには、業務ごとのマニュアル整備が欠かせません。
誰が担当しても一定レベルの業務が行える状態にすることで、急な欠勤時の対応や新人教育の効率化にもつながります。
クラウドによる情報共有とリモートワーク
3つ目のポイントは、クラウドによる情報共有とリモートワークの実施です。
複数の現場を同時に抱えることも多い施工管理者にとって、現場間の移動時間や書類の確認作業は大きな負担となっています。
図面や工程表、写真などのデータを一元管理することで、どこからでもアクセスできるようになり、現場に足を運ばなくても確認が可能となります。これにより、移動にかかる時間ロスを大幅に削減できます。
またリモートワークも可能となるため、労働環境の改善にもつながります。
人材採用・育成による適正な人員配置
4つ目のポイントは、人材採用や育成で適正な人員配置を実現することです。
現在、建設業界では深刻な人手不足のため、必要な人員配置ができなくなっています。
これを解消するためには経験者だけでなく、未経験者も含めて広く採用していくことが重要です。
未経験者であっても、早期に戦力化できるような研修制度を整えるなど人材育成にも力を入れる必要があるでしょう。
またシニア層の再雇用や女性施工管理者の登用も有効です。
労働時間の見える化
5つ目のポイントは、労働時間を見える化することです。
働き方改革を進めるにあたっては、まずは労働時間を正確に把握することが重要です。
ICカードやアプリでの出退勤管理など、労働時間管理の見える化を進めるのがおすすめです。
紙のタイムカードや口頭報告では把握できず見過ごされている残業などを把握し、適正な評価や労働環境の改善につなげましょう。
現場の声を反映した勤務制度の設計
6つ目のポイントは、現場の声を反映した勤務制度を設計することです。
勤務時間や休暇制度を設計する際には、現場の声を取り入れることが不可欠です。
トップダウンで制度を作っても、実態とあっていなければ運用されず、形骸化してしまいます。
たとえば、振替休日制度やフレックスタイム制の導入など柔軟な働き方を支援する制度は、実際に運用できるかをしっかりと現場に確認し、協力を得ながら設計するようにしてください。
まとめ
本記事では施工管理における働き方改革について、実行が難しい理由や実現のポイントなどについて詳しく解説しました。
施工管理の働き方改革を進めるうえでは、慢性的な人員不足や、それに伴う長時間労働など、さまざまな課題が存在します。
一方でクラウドやAIなどの技術も進歩しており、ICTの活用や業務の標準化、経営層の意識改革などを着実に進めていくことで、働き方改革を推し進めることは可能です。
株式会社ダイテックでは住宅業界に特化した施工管理アプリ現場Plusを提供しています。
現場Plusは図面などの書類の共有やオンラインコミュニケーションなど、施工管理に必要な機能を幅広く備えたオールインワンツールです。
施工管理の働き方改革をご検討の担当者様はぜひお気軽にお問い合わせください。
現場Plus公式サイトはこちら






